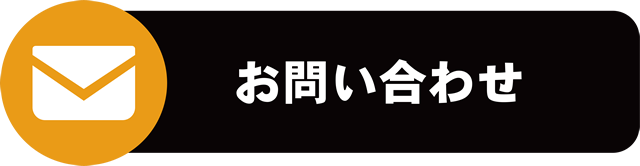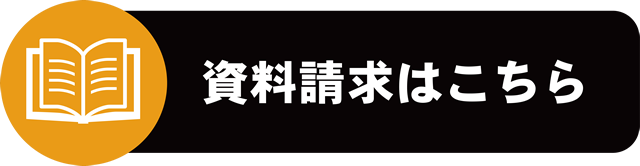第257話 賃金表を改定するベースアップの方法はリスクあり
2025-05-07
【受付開始】「成長塾224期」申込受付中!
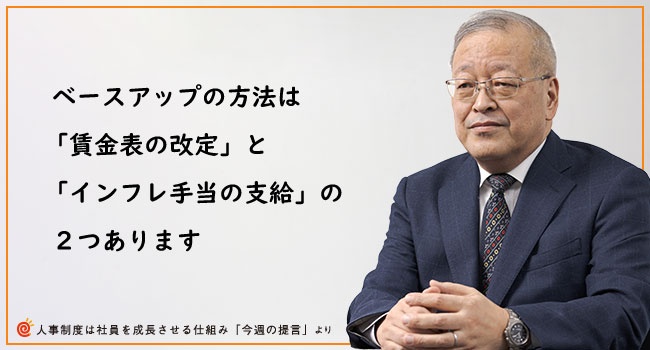
これからの日本では、賃上げが10年間継続する可能性があります。日本全体で賃金が上がることを考えると、中小企業も賃上げ率は5%を目標にしなければなりません。
この賃上げ率5%のうち昇給率が3%と考えると、その差である2%はベースアップです。このベースアップをどのように実施するかを考えなければなりません。
例えば、基本給の内訳が年齢給と仕事給であれば、そのどちらの賃金表を改定するのか、または両方とも改定するのかを決める必要があります。これから人事の仕事は増えていきます。
ベースアップにより賃金表を変える方法は毎年続くため、何年度の賃金表なのかを明らかにしておかなければ、採用や人事を担当している社員たちは混乱し、実際に昇給を決めるときも複雑になる可能性があるでしょう。
ベースアップの方法は人事部が決めるのではなく、経営者がその方法を決めることが大切です。もし仕事給が成長塾でお教えしている「成長給」であれば、社員に説明するときも成長給表を改定することで現在の成長等級と号俸数は変えずにベースアップすることができます。しかし、成長給表を変えないままベースアップをする場合は、社員それぞれの号俸数が変わることになります。2つの方法があります。
そしてもう一つ重要なことは、賃金表の改定をした場合、通常は賃金表を掲載している規程の改定をすることになりますが、毎年賃金表を変えるとなると、毎年改定した賃金表を労働基準監督署に提出することになります。ここで大きな問題になるのが、一度ベースアップのために改定した賃金表は、金額を下げる変更はできないことです。そのため、企業経営においては将来にわたって大きなリスクを持って行うことになります。
そうしたベースアップ対応の相談を受けたときは、私は賃金表を改定するのではなく、ベースアップ分を「インフレ手当」として支給する方法を提案しています。
日本では法律上支給しなければならない手当は「超過勤務手当」だけであり、それ以外の手当は一切法律上で支給を定められていません。このインフレ手当を支給する場合も、その支給目的を明らかにすることで金額の増減をすることができます。これにより、実はベースアップによって潜在的に問題が発生している「賞与」や「退職金」の計算への大きな影響を防ぐことも可能です。
一般的ではない、このベースアップへの対応は、方向性を間違えるとのちのち大きなリスクになります。ベースアップへの対応は、しっかり事前に検討しておかなければならないでしょう。
こうしたベースアップによる対応も、仕組みがあれば簡単にできます。今後も続く賃上げに仕組みで対応をしたい、そして、楽にベースアップを決めたいとお考えの方では、グループコンサルティング「成長塾」にご参加ください。
※「成長給」はENTOENTOの登録商標です。
【受付開始】「成長塾224期」の詳細・お申込みはこちらから!
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
※ 成長塾についてはこちら ※ 資料請求はこちら ※ 松本順市の書籍はこちら