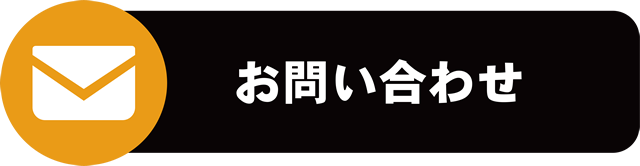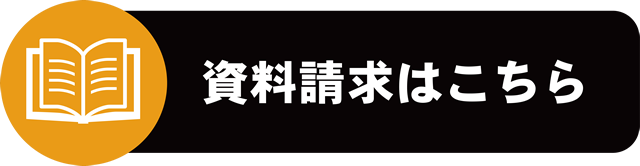第293話 人材採用、人事制度で大手企業に勝つ
2026-01-28 [記事URL]
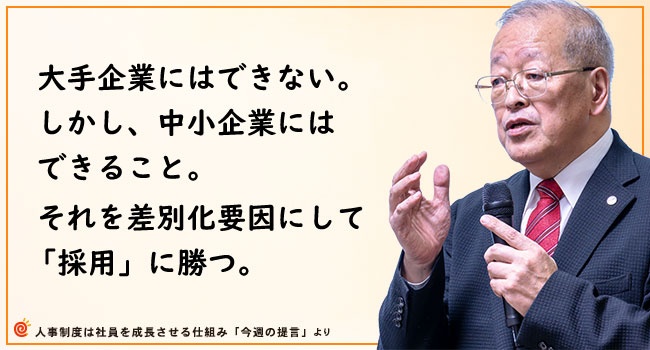
今、大手企業を中心に初任給が毎年大幅に上がり続けています。初任給が上がるということは、それと同時に在職社員の賃金も上げていかなければなりません。この状況に追随できる中小企業は、あまりないでしょう。
中小企業の経営者の中には「社員の定着も採用も大手企業には立ち打ちできない…」とあきらめている方もいると思います。しかし、中小企業でも「採用活動に“ある”差別化」を行えば、中小企業にふさわしい新卒を採用することができます。
重要なのは、大手企業にできないことを実施することです。
例えば「終身雇用」です。終身雇用は定年まで、あるいは長期にわたって同じ会社で働き続けられる雇用の仕組みのことです。人事制度によって、65歳を過ぎた社員を継続的に雇用することができます。
65歳ともなると、多種多様の仕事ができなくなることもあるでしょう。週5日勤務から週3・4日勤務といった働き方に変化する可能性もあります。そうした働き方の変化に合わせて処遇も変化する人事制度があることで、社員は安心して長く働き続けることができます。
65歳を過ぎても仕事ができることは、年金だけで生活するといった将来への心配がなくなります。これは今いる社員だけでなく、新卒にとっても大きなメリットになります。大手企業にはなかなかできない、中小企業ならではのメリットになります。
また、中小企業には基本的に出世競争がなく、入社した同期全員が一緒に成長できることも大きな差別化になります。お互いに教え合うことで、会社全体の業績を向上させることになるのです。
このように、まだまだ他にも多くの差別化を図る余地があります。大手企業だけが絶対優位というわけではありません。中小企業でも、大手企業に決して負けない人事制度をつくっていけばよいのです。
大事なことは、厳しいときにこそ知恵を出し、自社の良さを改めてアピールすることです。中小企業に本当に必要な新卒人材は「初任給が高いから選びました」という学生ではなく「経営者と一緒になって世の中に貢献していきたい」という学生ではないでしょうか。
そのための差別化できる人事制度をつくりたい方は、成長塾にお越しください。成長塾で、大手企業と差別化できる人事制度をつくることができます。申し込みは簡単です。
※「成長制度」はENTOENTOの登録商標です。
↓【新・3月スタート】「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
↓まずは「成長制度」について詳しく知りたい方はこちら↓(収録動画受講を新たに追加)
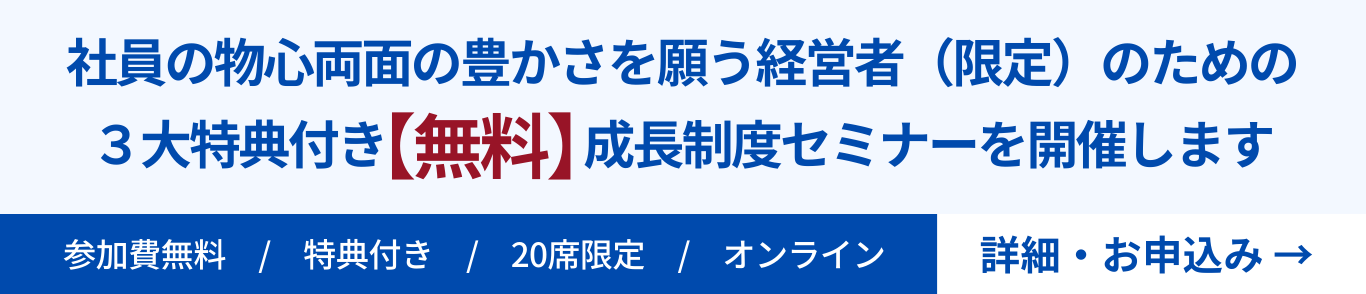
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
第292話 人事制度は社員のクレームで強くなる
2026-01-21 [記事URL]
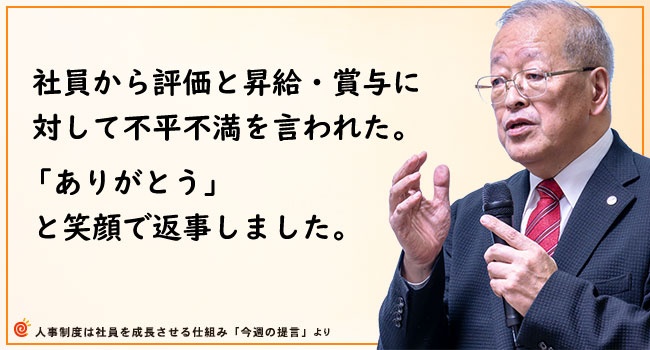
人事制度の目的は、一般的には社員を評価し、賃金や昇給・賞与(ボーナス)を決定するための仕組みです。つまり「給与や賞与を決めるために人事制度をつくっている」ということになります。
多くの場合、会社が決定した評価に対し、社員が意見や不平不満を言うことはないでしょう。しかし、もし社員が自分の評価に納得できていない場合は、昇給や賞与にも当然納得できなくなってしまいます。
人事制度は会社がつくるものですが、その評価に対して社員が「納得できない」という意見を伝えられないままであれば、不満を持ったまま働くか、または諦めて会社を辞めるしかありません。
そもそも、評価に納得できない理由は明確です。上司と部下である社員本人で評価している点が異なるからです。上司同士によっても評価の甘辛があるくらいですから、上司と部下で評価に違いがあるのはあたり前のことです。しかし、この違いを放置したままでは、上司の指導は効果的にはなりません。
どれほど上司がマネジメントスキル(部下を正しく指導するスキル)を身に付けていたとしても、部下が上司の評価に納得していない状態であれば、その成長を促すことはほとんど不可能でしょう。
そこで、部下が「評価に納得できない」と訴えてきた場合には、その声をしっかりと受け止め、評価の基準や理由を説明することが必要です。会社の評価の決め方が公平で、十分に説明できれば、社員は元気に成長します。
それでも納得できない場合は、きちんとその理由を聞き、納得するまで説明しなければなりません。場合によっては、部下の主張が正しいこともあるため、その場合は評価の見直しが必要になります。
人事制度は社員の成長のためにつくり、運用していくものです。
そのため、会社組織の成長に合わせて人事制度も見直しが必要となります。一番大切なのは、社員が納得できるように制度を改善していくことです。
多くの会社では、お客様からのクレームに対応し、顧客管理の仕組みを見直しています。その結果として顧客満足度が高まり、顧客の定着率や顧客単価も高めています。つまり、クレーム対応によって顧客の満足度を高め、会社の業績を伸ばしているのです。
同じように、人事制度も社員からのクレーム(不平不満や意見や要望)があるからこそ、より社員の成長につながる良い仕組みに進化していきます。
社員の「評価や昇給・賞与に納得できない」といったことを感じた場合は、その声を無視せず、しっかり聞いて対応していくことが求められます。これは、人事制度を進化させる上で最も大切な原動力となるでしょう。
社員の成長とともに人事制度もより良いものにしていきたい、そんな制度をつくりたいと考えている方は、グループコンサルティング「成長塾」で正しいノウハウを学びに来てください。人事制度のつくり方だけでなく、見直しの方法まで詳しくご案内いたします。グループコンサルティング「成長塾」は、ここからお申し込みできます。
※「成長制度」はENTOENTOの登録商標です。
↓【新・3月スタート】「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
第291話 部下指導を有効にするためには部下に成長のゴールを示すことです
2026-01-14 [記事URL]
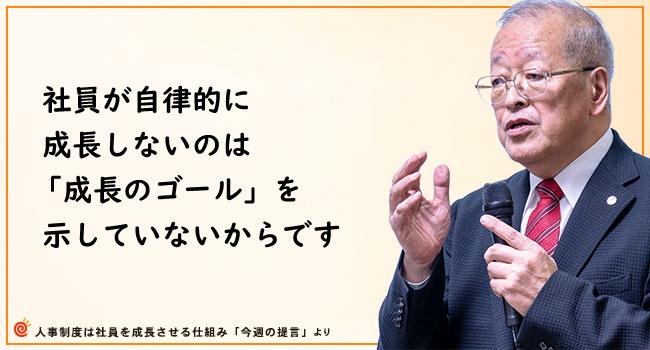
部下指導には、さまざまな「マネジメントスキル」が必要だと考えている方が多いでしょう。しかし、実際にマネジメントスキルを身に付けたからといって、部下が思った通りに成長したことはあったでしょうか。この問いに「イエス!」と答えられる上司は、そう多くないはずです。
部下が自律的に成長しない本当の理由は、部下に「成長のゴール」を示していないからです。成長のゴールを示すことで、部下は一つの例外もなく自らそのゴールに向かって成長しようとします。
ここでいうゴールとは「次の階層まで成長するための必要な力を身に付け、成果を上げられるようになること」です。私たちは、このゴールを「成長シート」というシートにして部下に示します。
基本的に、新卒で入社後は「一般階層」として現場で働くことになります。そこで、まずは一般階層でどのようにすれば成果を出せるのかを整理し、1枚の成長シートにまとめてください。そして、この成長シートを「成長のゴール」として事前に示してから部下指導をはじめるのです。
この成長シートは一般階層を卒業した上司がモデルです。つまり、上司が部下指導をする際「あなたの成長のゴールは、今の私です」と示すことになるのです。成長シートと上司を通じて成長のゴールを示すことで、部下は「どうすれば優秀な社員になれるのか」を事前に知ることができます。
成長したいと思っている部下に、無理に発破をかける必要はないでしょう。部下指導をするためには、まずは部下に成長のゴールを示すこと。これが最も部下を成長させる鉄則であり、効果的であることを知ってください。
全ての部下を成長させるための成長シートは、グループコンサルティング「成長塾」でつくることができます。その正しいノウハウを学びに来てください。
グループコンサルティング「成長塾」は、ここからお申し込みできます。
※「成長制度」「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
↓「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
第290話 人生成功の鍵は目標設定にあり
2026-01-07 [記事URL]
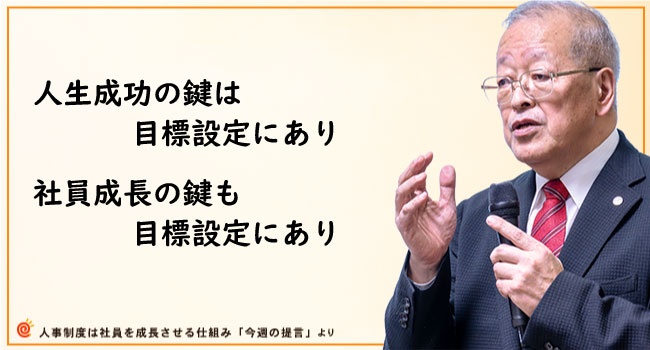
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
新年にあたり、多くの方が「目標設定」をされたと思います。一般的には今年1年間の目標を設定しているでしょう。しかし、最も大切なのは「人生の目標」です。何のために生まれ、何をしようとしているのか。それを確認することです。
これからの日本は、かつてないほど厳しい環境が続きます。例えば「賃上げ率の大幅な上昇」です。最低賃金は毎年5%以上上昇することになるでしょう。2026年でも5%以上上がることは必至です。それに応じて、初任給や中途採用の賃金も上昇することは間違いありません。
こうした厳しい時代に私たちは生まれ、人生を過ごしています。その中で、何を人生の目標にするのか考えることはとても重要でしょう。
毎年の目標設定の前提には、この「人生の目標」があります。人生の目標とは「自分はどのように生き、どのように社会に役立ちたいのか」といった、より根本的な方向を目指す目標のことです。
このことを考える良い機会が、この1月の年頭だと思います。ぜひ、自分の人生の目標を考えたうえで、今年の目標設定をしてください。
「成長シート」がある会社は、とても簡単に今年の目標設定ができます。成長シートとは、社員が成長するために身に付けるべき知識技術や行動を整理したシートで、人材育成や人事評価の土台になるものです。
一人前の社員になること(第1段階)、人を育てることができるようになること(第2段階)、経営者と一緒に会社を通じて世の中を良くしていくこと(第3段階)。そのために必要なことを成長シートで示すことで、それぞれの成長段階に応じた目標を立てることができます。
この成長シートでの目標管理は、達成率で評価しないことが特徴です。どれだけ挑戦的な目標を立てたか、それがどれだけ成長につながるかが明確だからです。
今年1年間の大いなる目標を、成長シートで設定してください。それでは、今年も1年よろしくお願いいたします。
※「成長制度」「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
↓「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
第289話 稼げる社員への成長は可能だ
2025-12-24 [記事URL]
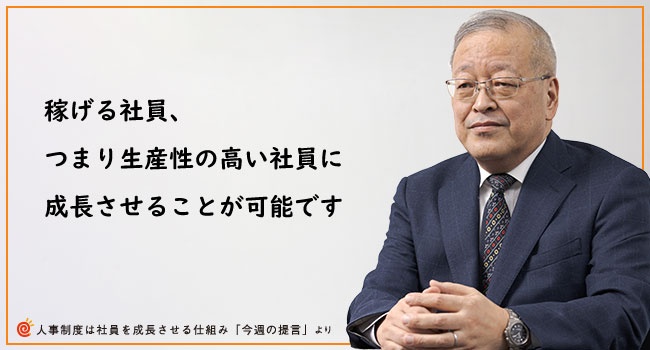
日本では、基本的に「お金」の話をすること自体がタブーとされているように感じます。
そのため、経営者の「頑張った社員にはたくさん給料を出す」といった話は、社員にはあまり受け入れられていない可能性があります。
しかし、現在の日本では生活費が増え続けているため、自分の稼ぎで生計を立てるには収入を増やす努力が必要です。そもそも、収入が増えることは組織の一員として世の中に貢献した結果です。そのためには、どのような成果を上げることでどれだけ収入を増やせるのかを社員に示し、教育しなければなりません。
特に、成果の中で最も大切なのが「時間粗利」です。時間粗利とは、社員一人が1時間でどれだけ効率的に利益を生み出しているかが分かる、いわば生産性を表す指標です。この時間粗利を計測して数値を確認することで、社員は自分の生産性を明確に把握することができます。
そして、その成果は組織として社会に貢献した結果であり、給与にどのように反映されるのかを理解することで、社員はさらなる生産性向上に向けて取り組むようになるのです。
私自身、前の会社で入社時点の時間粗利2,600円から5,600円まで向上した過程を経験しました。2,600円のときは毎日忙しく、常に大変な状態でした。そこから5,600円まで向上したのは、社員のやる気や頑張りよりも生産性を上げるための「仕組み」をつくり、しっかり運用したからです。5,600円の現場は楽々でした。その結果として、社員の力が2倍以上になり、それと同時に生産性も2倍以上になりました。
このように、社員を成長させるには「稼げる社員」に育てることが重要です。賃上げ率がどんどん高くなっている日本で、社員を会社に定着させたり、新しい社員の採用を進めたりするには、社内の「稼げる社員」を増やすことが必要になります。
その方法は簡単で、社員の生産性を高めることです。生産性を向上させる最大のヒントは、社員が自分の生産性を毎日把握できるようにすることで手に入ります。
生産性の高い日もあれば、低い日もあります。しかし、その差が生じている理由を1か月後に確認しても気づきにくいでしょう。そこで、生産性の数字を毎日出すことで、自分にとって最も効率の良い仕事のやり方を見つけやすくなり、やがてその高いやり方が「仕組み」へとつながっていきます。仕組みにして他の社員に共有することで、会社全体の生産性向上にも大きく貢献します。
上司のマネジメント力がどれほど優秀であっても、現場の社員の生産性を上げるのには限界があります。そこで、現場で働く社員の生産性の高いやり方を日々確認し、上司はそれを全体に共有化するのです。
生産性向上の答えは常に現場にあります。経営者は「頑張った社員にはたくさん出す」といった説明ではなく「生産性を向上することで、全員にたくさん出せる」と社員に説明し、現場の社員が仕事を楽しみながら生産性を高められるようにしてください。
生産性の高い社員へ成長させるには「仕組み」が重要であり、その1つが「人事制度」です。人事制度とは、社員の成長やさまざまな働き方を支援し、評価・賃金を高める会社の仕組みです。この人事制度をつくりたい方は、グループコンサルティング成長塾にお越しください。
※「成長制度」「時間粗利」はENTOENTOの登録商標です。
↓「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
冬期休業のお知らせ(2025年度)
2025-12-17 [記事URL]
弊社では誠に勝手ではございますが、本年度の冬期休業日につきまして、以下の通りとさせていただきます。
◆ 休業期間 2025年 12月26日(金)~2026年 1月4日(日)
【セミナー・研修へお申込みいただいた際】のご請求書の郵送につきましては、以下の通りとなります。
12月19日(金)16時30分までにいただいたお申込みにつきましては、25日(木)までにご請求書を発送いたします。
【ご注文いただいた商品の発送】につきましては、以下の通りとなります。
●お支払方法【代金引換便/払込書】でのお申込
12月19日(金)16時30分までにいただいたご注文につきましては、25日(木)までに発送いたします。
※在庫切れの場合にはその限りではございません。ご了承ください。
●お支払方法【銀行振込】でのお申込
12月19日(金)16時30分までにご入金いただいたご注文につきましては、26日(木)までに発送いたします。
12月19日(金)16時30分以降の商品のご注文・ご入金につきましては、1月5日(月)以降に発送させていただく可能性がございます。
なお、冬期休業中もFAXやEメールによるお問合せは受付けておりますが、12月22日(月)8時以降のお問い合わせ等につきましては、2026年1月5日(月)以降に順次対応させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
第288話 新卒採用するための初任給の説明方法は2つ
2025-12-17 [記事URL]
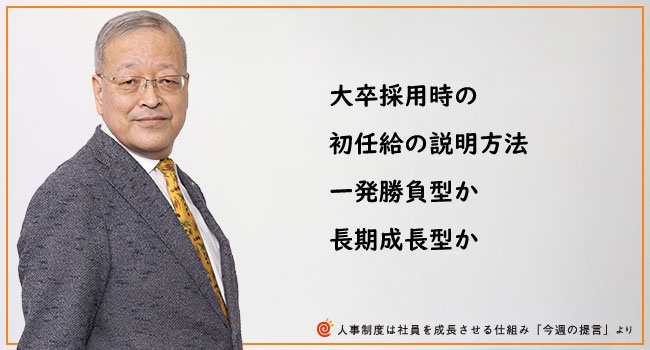
今の時代において、新卒採用するための賃金の説明方法は2つあります。1つ目は初任給を大きく上げる方法、2つ目は入社後どのように増えていくかを明示する方法です。
例えば、前者は初任給30万円を提示するが、その後の昇給の方法は分からない。後者はそれに対して初任給は24万円だが、その後どのように増えていくのかを提示します。
初任給とは新卒で入社した社員が、最初に会社からもらう月給のことです。多くの会社が大卒採用に力を入れていますが、最近、ほとんどの大学生は初任給が高い会社を選ぼうとしています。
これは、多くの大学が就職指導の際に「初任給が高い会社を選びましょう」と教えているためです。そのため、初任給が低い会社は、就職活動をしている大学生からはターゲット外とみなされる可能性があります。
しかし、中には初任給が高くても、その後も本当に給料が増えていくのか心配している大学生もいます。そこで、今の初任給が30万円ではなく24万円の企業であれば、入社後どのように給料が増えていくのかを説明することが新卒採用に求められているのです。
実際、初任給が高い会社に入社後「この先も昇給されるか分からない」と不安になる新卒社員が多く存在します。ですから、初任給が低かったとしても、入社後の成長によっては他社の初任給30万円を上回る給料になると仕組みで説明することで、大学生に大きな安心感を与えて採用することができるのです。
初任給が高くないからといって採用をあきらめる必要はありません。入社後、しっかりと給料が増えていく仕組みを持つ会社であることを説明すべきです。この説明に納得する大学生を採用したいものです。
会社が社員の成長や昇給を決める仕組みをオープンにしていることを、人事制度を使って明確に示すことが必要な時代になりました。自社の人事制度を学生に見せながら説明することで、採用力を強めることができます。
入社後にどのように給料が増えていくかを説明できる人事制度をつくりたい方は、グループコンサルティング「成長塾」にお越しください。
※「成長制度」はENTOENTOの登録商標です。
↓「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
第287話 ベンチマーキングする対象は社外ではなく社内にあり
2025-12-10 [記事URL]
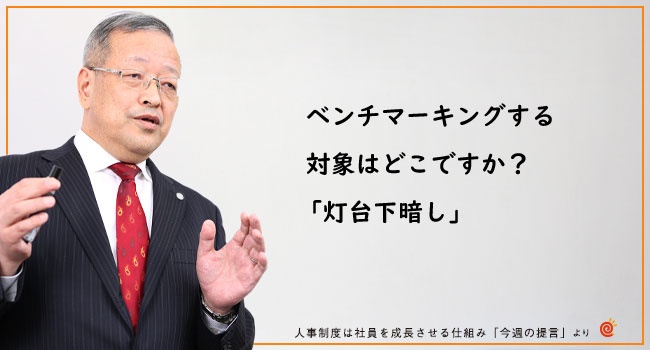
経営者が企業をさらに成長させようと考えたとき、多くの場合は「同業界で自社より成長している企業」から学ぼうとします。そして、その企業の良いところを自社でも真似て実践しようとするでしょう。
ですが、こうした他社の取り組みや方法を自社に取り入れようとする「ベンチマーキング」が成功する可能性はほとんどありません。なぜなら、他社をモデルにして取り組む場合、大前提として社員や仕組み、組織文化など、自社の状況が全て他社と同じである必要があるからです。
しかし、実際にこれら全てが同じだという会社は一社もありません。そのため、ベンチマーキングを行っても、自社の弱点やダメな部分ばかりが目立ち、ただ反省する結果になることが多いでしょう。
ベンチマーキングの考え方を生かすのであれば「自社にとって有効な方法を取り入れる」ことが重要です。もっとも有効な方法は「自社の優秀な社員をモデルにする」ことです。ここでいう優秀な社員とは、自社で一番高い成果を上げている社員のことです。ここでは、絶対的な優秀さは求める必要がありません。
身近にいる優秀な社員を日々見ることで、何をしているのか、どのような特徴があるのかを知ることができます。多くの場合、その社員が成果を上げるために日々行っていることが可視化されれば、他の社員も「自分にもできそうだ」と考えるでしょう。
変化が激しい今の時代においては、外部の会社をベンチマーキングして参考にすることはほとんど不可能です。しかし、自社にいる優秀な社員のやり方を真似ることは決して難しくありません。これからは、この優秀な社員をモデルにしてつくる「成長シート」が役に立つ時代です。
「成長シート」とは、優秀な社員の行動や考え方をまとめたツールのことです。もちろん、ここでいう「優秀さ」はあくまで相対的なもので、他の社員と比べて優れているという意味です。
ある経営者は、「自社に優秀な社員がいるなら苦労はしない」といいます。しかし、相対的に見れば、優秀な社員は必ず自社にいます。その社員をモデルにして成長シートをつくり、その内容を全社員に教育してください。これが、これからの時代に社員全員を優秀にし、業績を上げるもっとも近道であることを知ってほしいと思います。
社員を全員優秀にしたい、業績を上げたい、そして賃上げしたいと考えている方は、自社の成長シートをつくることができるグループコンサルティング「成長塾」をご受講ください。
※「成長制度」「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
↓「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
第286話 高賃上げ時代に対応するための賃金制度の見直しについて
2025-12-03 [記事URL]
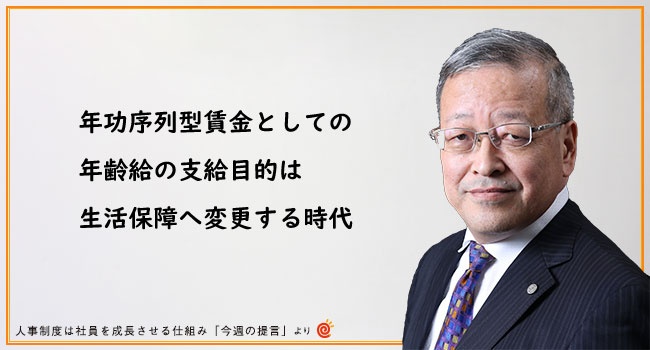
高い賃上げが求められる現代では「年齢給」をやめなければならないのです。
日本の多くの企業では、基本給の中に年齢給があります。年齢給とは年功序列型賃金の一つであり、社員の年齢に応じて増えていく賃金です。しかし、年功序列型賃金が有効だったのは、戦後の高度成長時代や安定成長時代に限られます。
その当時は、社員として長く勤務することで経験やスキルが蓄積され、会社への貢献度が高くなることを前提に年功序列型賃金は機能していました。現在は多くの経営者がその役割を終えたことに気づいています。そのため、今後年齢給をどのように廃止すればよいかという相談が多くなりました。
このとき、年齢給を廃止すると社員の賃金が下がってしまうのではないかと心配されがちですが、年齢給を廃止しても現在の社員の賃金総額は変更しません。この原則(「何も足さない何も引かない」)を守ることが最も重要です。
その一方で、最近は若い世代の昇給額を多くしたいという相談が増えています。しかし、若い社員の昇給額を増やせば、今度は中堅職以上の社員の不満につながりやすい点も認識しておく必要があるでしょう。こういった場合の昇給額を増やす方法は、年齢給を「生活保障給」として支給することです。
生活保障給は社員の成長や企業への貢献に関係なく、基本的な生活を守るために一定期間加算します。特に新卒社員の場合、通常は成果を上げるまでに長い年数が必要になります。それまでの間昇給しないことは現実的ではないでしょう。
企業は新卒社員を成長させるために多くの時間や費用をかけて教育しています。学校時代とは違い、授業料を請求することはありません。そこで、生活保障給として昇給するのは社員として一人前になるまでにかかる標準的な年数の間だけで充分でしょう。
例えば毎年5千円から1万円程度の昇給でも、生活保障給として支給すれば、中堅層やベテラン層の社員たちの不満にはなりません。「社員の成長による昇給」と「生活保障のための昇給」では、目的が根本的に異なるからです。
賃金制度は経営者それぞれの考え方を可視化してつくりますが、経営者の考えが間違いということは100%ありません。しかし、賃金に関する目的や方針をきちんと社員に説明できなければ、やがて不平不満の温床となります。社員が退職する大きな理由の一つです。経営者自身の想いを込めた賃金制度へ安心して見直しを進めてください。
賃金制度の根本的な見直しについて学びたい方は、グループコンサルティング「成長塾」を受講ください。賃金制度のつくり方や見直し方法について、すべてのノウハウを提供しています。これからの高賃上げ時代に対応するための賃金制度のつくり方も学ぶことができます。一生の財産です。
※「成長制度」「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
↓「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
第285話 全社員の「暗黙知」を合体させて成長シートをつくる
2025-11-26 [記事URL]
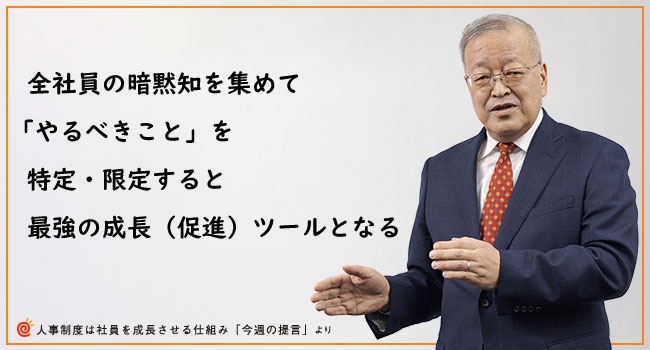
社員一人ひとりが、さまざまな経験をしながら今に至っています。そうした社員それぞれの経験を1つにまとめてつくるのが「成長シート」です。
しばしば「成功事例の共有化」というテーマが話題になりますが、成功事例を常時明確に示している企業はほとんどありません。そのため、それはいわゆる「暗黙知」の状態であり、他の社員が同じように成功できるよう説明することは、とても難しいのが現状です。
そこで活用するのが「成長シート」です。まずは全社員の成功事例を集め、その中から最も成果を上げるのに貢献度の高いものを成長シートに記載します。
最も成果を上げることができる業務や知識といった内容を成長シートにまとめて共有化することで、全ての社員が最も高い成果を簡単に上げることができるのです。結果として、企業としても生産性高く業績を上げられるようになります。
いつの時代も同じですが、「やること」を増やしても成果は上がりません。やることを増やせば増やすほど成果が上がらなくなることは、誰もが一度は経験していることでしょう。
「やること」は限定しなければならないのです。
ですから、社員が30人いれば30人全員の全ての成功事例を共有化するのではなく、その中で最も高い成果を上げることができる成功事例に絞って成長シートに記載し、全ての社員に共有化するのです。これにより、30人全員が最も高い成果を上げることができるのです。
これに加え、成長シートは職種、階層ごとにつくります。一般・中堅・管理の3階層ごとに成長シートをつくることで、それぞれの階層まで成長している社員が最も早く、簡単に成果を上げることが可能になります。なぜなら、成長シートを通じて「自分が今いる階層で高い成果を上げるやり方」を知ることができるからです。このように、成長シートは全ての社員の成長を促し、短期間で最も高い成果を上げることができるツールになります。
さらに、一部の社員が環境の変化に適応して成果を上げる事例が出てきますので、そのことも成長シートに取り入れて全社員で共有化することを継続してください。このように、一度成長シートをつくれば社員はエンドレスに成果を上げ続けることができるようになります。
こうした共有化の仕組みの変更により、企業の業績は考えられないほど早く向上させることが可能です。ぜひ、成長シートを活用してください。
成長シートのつくり方を実際に学びたい方、そしてすぐに活用して全ての社員の成果を上げたい方は、ぜひグループコンサルティング「成長塾」にお越しください。
↓「成長塾」のお申し込みはこちらから↓
※「成長制度」「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
- ENTOENTOについて
- 会社概要
- 代表ご挨拶
- 事業理念
- 由来
- プライバシーポリシー
- 商標・著作権について
- 情報セキュリティ方針
- 採用について
- 採用トップページ
- 募集要項
- ENTOENTOの成り立ち
- 先輩社員インタビュー
- Q&A