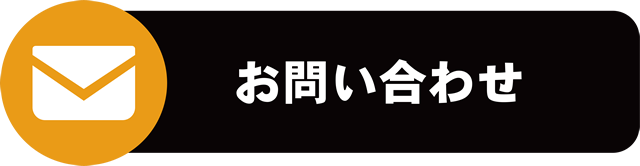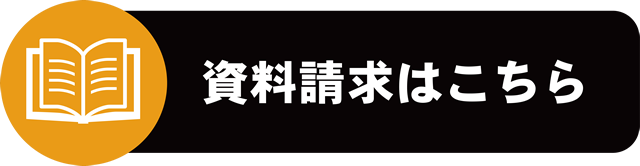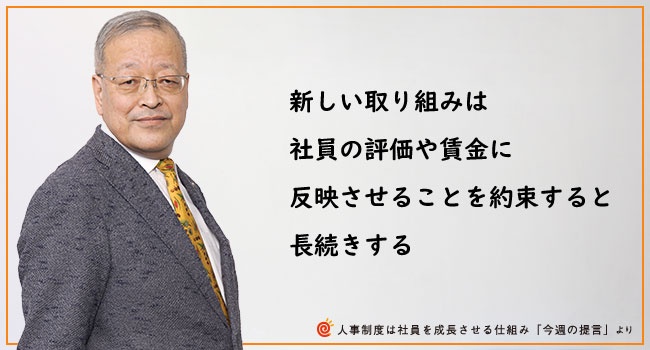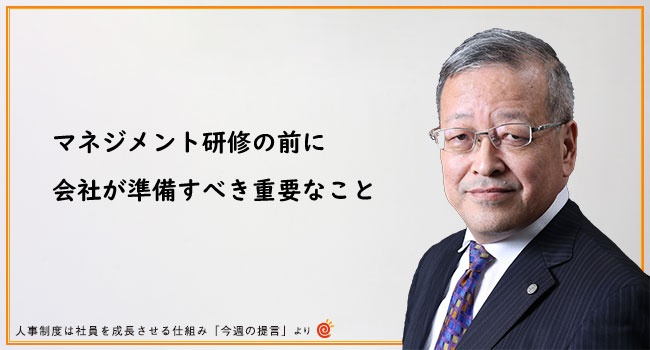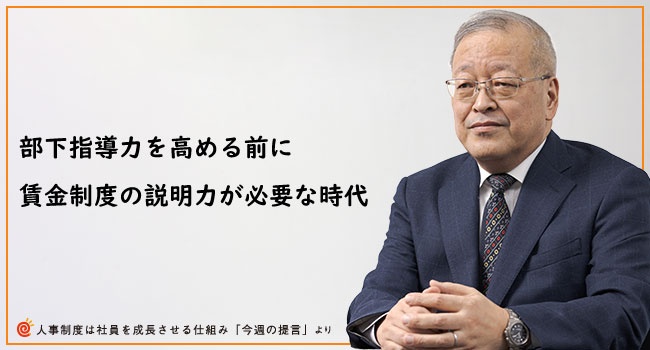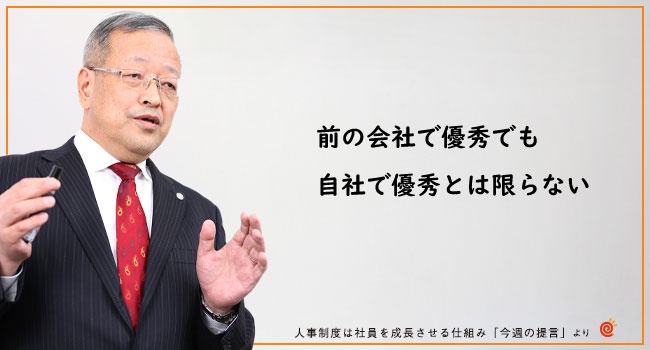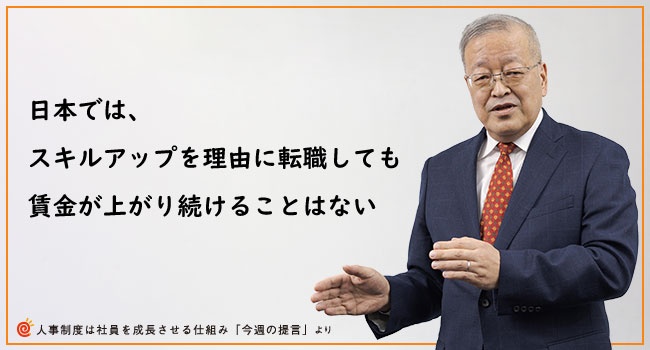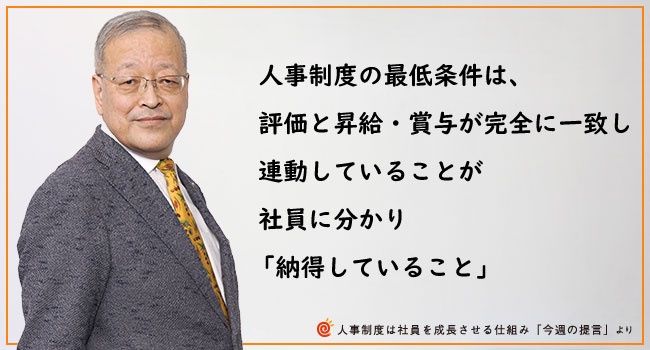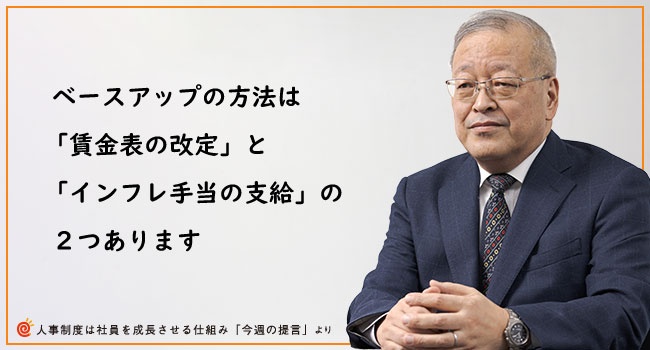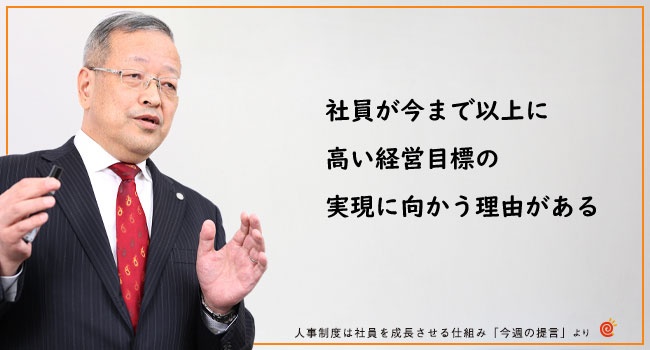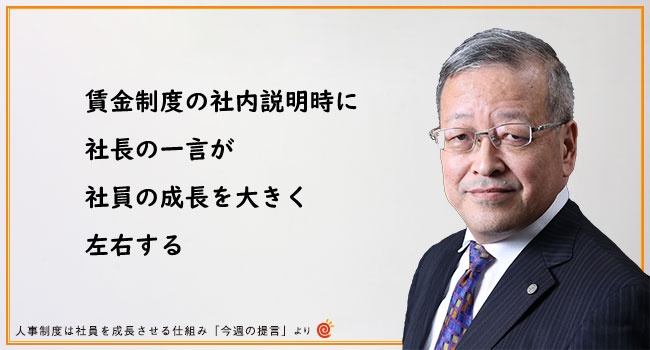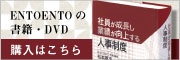第255話 賃金の違いを説明できる会社になること
2025-04-23 [記事URL]
賃金制度をつくるときに経営者が考えていることは「いかに社員の成長に合わせて賃金に差をつけるか!」です。
もちろんこれは経営者の立場として考えれば当然のことでしょう。しかし、社員にとっては一番嫌な考え方ともいえます。経営者が常日頃「皆で一丸となって一緒に成長してほしい」と発言しているにもかかわらず賃金に差をつけることは、社員からすれば社員同士で競争させようとしていると考えてしまうのです。
誰もが賃金はたくさん欲しいと思っています。それは当たり前のことです。万が一差をつけるのであれば、他の誰よりもたくさんもらえるような社員になりたいと思う社員は必ずいるでしょう。もしそれが成果の高い社員であれば、他の社員に教えなくなり、結果として会社全体の業績にも大きなマイナスの影響を与えることになります。
では、この経営者の考えを社員に正しく伝える内容は何でしょうか。それは「社員の成長に伴って賃金が増える」と説明することです。この説明ができなければ、賃金の違いに社員が納得せず、賃金制度に賛成することもないでしょう。
ここで「成長シート」があれば、賃金額が違うのは社員の成長に合わせていると説明することができます。例えば、成長シートで4人の社員を評価した結果、その点数(成長点数)がそれぞれ20点、40点、60点、80点だったとします。この中で一番賃金が高くなるのはもちろん80点の社員です。成長点数は社員の成長の度合いを可視化した数字であり、その点数によって賃金が違うことを社員は理解します。
入社した段階では全ての社員は20点からスタートしますが、やがて成長して40点になれば、20点のときよりも賃金は増えることになります。このように、この会社は成長することで賃金が増えると明確に分かるようにしなければならないのです。
この仕組みがあれば、社員は「なぜあの人は自分よりも賃金が高いのか?」と経営者に直接聞かずともよくなります。それはその社員が自分よりも成長点数が高いことが明確になっているからです。
賃金制度で最も大事なことは、賃金に差をつけるためではなく社員の成長によって賃金がどのように増えるかを説明できる仕組みであることです。この説明によって、社員はこの会社では成長に伴って賃金が増えていくと理解するでしょう。
そして、社員がこのことを理解したうえで、さらにもう一つ大切な話をしなければなりません。それは賃金を増やすためには会社の業績が良くなければならないことです。
確かに成長点数が20点から40点、60点と成長していけば賃金が増えることになります。しかし、その大前提には会社の業績が良くなければなりません。仮に成長点数が増えたとしても、会社全体の業績が前年より下回った場合は、賃金は増やすことができない現状があります。
実際、コロナ禍のときには業績が厳しくて社員の昇給ができなかった会社はたくさんあります。そういったときに、昇給ができないのは社員の成長よりも会社の業績が影響していたことが分かるようにする必要があるのです。
昇給の話は、実際に昇給するときにしかしないのが通例です。しかし、そのときに社員から納得できないと言われても、その場で対応することはできないでしょう。
会社の業績によって昇給額がどう変わるのか、そして成長によって昇給額が違うということを前もって説明しなければなりません。この説明を通じて、社員には昇給額は自分の成長以上に会社の業績が影響していることを知ってもらわなければなりません。それは誰もが増えてほしいと思っている賃金を、どのように増やすのかを学ぶことになるでしょう。
会社の業績が高まれば全社員の賃金が増える。賃金を増やすためには自身が成長すること、そして社員同士教え合い学び合うことで、全員で成長して会社の業績を上げることがとても大事だと、社員は仕組みを通じて理解します。
この仕組みをつくる経営者は、もちろん社員を大切にしていて、物心両面豊かにしたいと願っている経営者であることは確かです。そのことを早いタイミングで社員に理解してもらえるためにも、その想いを仕組み上で説明できることが重要になります。
これから社員の賃金が上がっていくことは目に見えるようになります。賃金に対しての関心が高まっている今こそ、社員には賃金が増える仕組みをしっかりと理解できるようにする会社にしならなければならないでしょう。
この仕組みをつくりたい方は、グループコンサルティング「成長塾」にぜひご参加ください。お申込みは簡単です。
【受付開始】「成長塾224期」の詳細・お申込みはこちらから!
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。