臨時休業のお知らせ
2025-07-10 [記事URL]
平素より大変お世話になっております。ENTOENTOです。
今年の成長塾第20回全国大会開催に伴い、次の日程で臨時休業させていただきます。
◆ 休業日 2025年7月18日(金)
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2025-07-10 [記事URL]
平素より大変お世話になっております。ENTOENTOです。
今年の成長塾第20回全国大会開催に伴い、次の日程で臨時休業させていただきます。
◆ 休業日 2025年7月18日(金)
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2025-07-09 [記事URL]
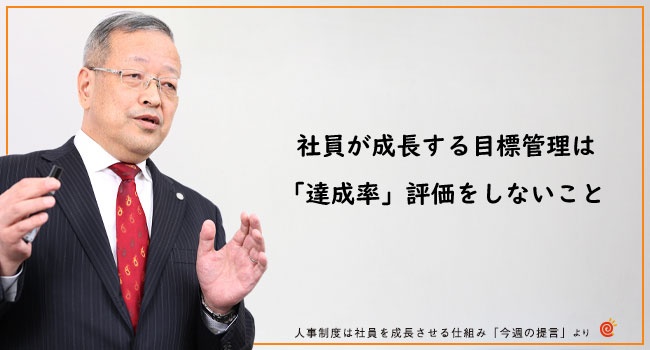
多くの会社で目標管理制度を導入していると思います。目標管理制度を導入する目的はもちろん社員の成長であり、そしてその結果として会社の業績の向上にあります。
目標管理をしているほとんどの会社で、結果である実績が立てた目標を満たしているかどうかを判断する「達成率」という評価項目をつくっています。この達成率評価があるために、やがて社員は高い目標を設定しないようになります。
目標管理制度を導入した1年目は、ほとんどの社員が高い目標を設定し、社長は社員それぞれの目標の高さに感心していたことでしょう。しかし、導入から2年目になると、社員の目標は1年目とは打って変わってとんでもなく低い目標になります。
なぜなら、社員は最初から目標を低くした方が達成しやすく、簡単に達成率評価が高くなると気付くからです。これでは経営目標を実現することはできないと危機感を感じた会社は、やがて会社全体の目標を社員それぞれに割り振るようになっていきます。
このことを、一般的に「ノルマ管理」といいます。ご存知の方も多いでしょうが、この「ノルマ」という言葉はロシア語です。戦後、シベリア抑留から帰ってきた日本人が伝えたのが「ノルマ」という言葉です。この言葉は暗い過去があるだけではなく、今もあまりイメージのいい言葉としては使われていません。
ノルマを課された社員が笑顔で仕事することはまずないでしょう。その上、さまざまな理由を述べて「そのノルマの実現は無理である」と上司に訴えていることが往々にしてあります。
高い目標を立てた社員が成長することは、どの会社でも経験しているでしょう。しかし、社員が高い目標設定を嫌がるようになれば、その瞬間から社員は高い目標から低い目標にすることばかり考えるようになり、成長しなくなってしまいます。当然、会社の業績も良くなることはないでしょう。
このように、社員の成長を阻害するような目標管理をやっている会社がほとんどです。社員が常に高い目標を設定するよう、目標管理制度は大改革をしなければなりません。実は、その方法はとても簡単です。
「成長シート」を運用されている会社であれば、社員にはその成長シートで目標設定をしてもらいます。そしてこの目標設定をしたのち、結果である実績(成長点数)で昇給・賞与を決めます。
極端な例ですが、成長シートで評価した点数(成長点数)が20点の社員が、80点の目標を立てたとします。目標を立てた社員は、その実現に向けて日々努力することになるでしょう。
社員はその高い目標に向かってとても成長しますが、1年で20点から40点まで成長することは十分あっても、80点を実現することは到底できません。1年後に40点になった場合、昇給・賞与は実績の40点で決めることになります。
仮に、同期の他の社員が20点からスタートして、目標を40点にしたとしましょう。本来であれば、この辺が妥当な目標かもしれません。
しかし、40点を目標にした社員が実現できるのは30点から35点くらいが一般的です。実績は高い目標を掲げて挑戦した社員の方がもちろん高くなります。実績で評価するのであれば、昇給・賞与には当然違いが出てきます。この説明を社員に向けてできるような仕組みでなければなりません。
高い目標を掲げて実績を上げた社員は「目標が高いのは大変だがやりがいがある。だからこそ高い実績を上げることができた。これからも高い目標を掲げて挑戦していきたい」と、他の社員に説明するようにしてください。
会社としては、高い目標を掲げた社員は成長し、その実績に見合って昇給・賞与が高いことを社内に示せばいいのです。高い目標を掲げることで成長し、処遇において不利になることもない。これが正しい目標管理です。目標達成率は社員が成長するような評価項目になっていないことを知ってください。
正しい目標管理制度にするためには、正しい人事制度「成長制度」がなければなりません。成長制度の構築はグループコンサルティング「成長塾」で行っています。このグループコンサルティング成長塾にご参加ください。
※「成長シート」「成長制度」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
2025-07-02 [記事URL]
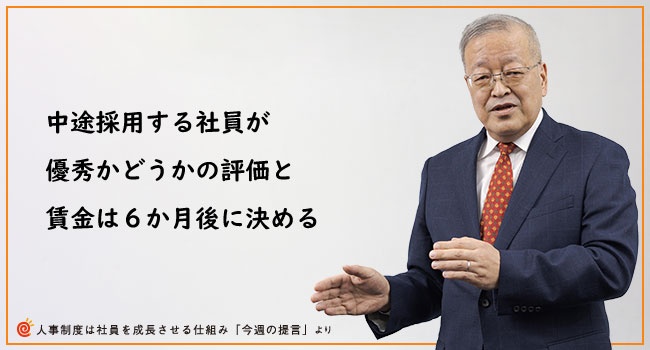
日本では、たとえ業種や職種が同じ会社で優秀だったという社員が自社に転職してきたとしても、同じように優秀だと評価されるとは限りません。
面接の時点では優秀だと思って採用しても、採用後に実際に働いてから評価してみると肩を落とすような結果になることがあります。さらに、採用時の賃金は優秀だと思って決めた金額のため、同じ評価の在職社員よりも高い賃金であることが多く、これが後々大きな問題になってしまうことがあります。
こうした採用の失敗をしないためにも、中途採用をする際は、ある方法を活用して採用しなければなりません。それは自社の「成長シート」を活用して採用面接をすることです。
成長シートは「自社にとって優秀な社員」を基につくられたシートです。採用面接では応募者に成長シートを見せて、記載されている期待成果・重要業務・知識技術・勤務態度の成長要素がそれぞれどのくらいできるのか確認します。
もちろん、このときの評価は応募者本人の自己評価であり、自社における正式な評価ではありません。正式な評価は入社後、最低でも半年間は必要です。とはいえ、試用期間後の賃金を決めるためにも、入社面接の時点で成長シートを活用して、自社における優秀な社員かどうかの確認をしなければなりません。
そしてその際、併せて最終的な評価は採用から半年後の段階で確定すると応募者本人に説明します。これにより、面接時点での評価は高くても採用後は評価が変わる可能性があることを応募者は理解し、「できない」ことを「できる」と自己評価することはなくなります。多くの場合、面接時にこの成長シートで正しい自己評価を考えるようになるでしょう。
どうしても優秀な社員を採用したいという場合は、半年後に評価と一致するよう賃金の見直しができる仕組みをつくらなければなりません。中途採用をしている企業は、この仕組みをつくっておかなければならないのです。
この仕組みがなければ、面接の段階で成長シートに記載されていることを「できる・分かる・守れる」と応募者が一方的に話し、それを会社側が鵜呑みにして高い賃金で採用してしまうことになります。
黙っていても中途社員の賃金が上がっていく時代です。万が一、優秀な社員だと勘違いをして高い賃金にしてしまえば、その後に変更することは困難な状況になりかねません。
前勤務先の会社で優秀かどうかではなく、入社後の自社において優秀であるかどうか。そしてその優秀さを面接時点で判断するために成長シートを活用します。こういったことを仕組み化しなければなりません。
この仕組みによって、中途採用する全ての社員の評価と賃金を一致させることができるようになるでしょう。この仕組みをつくっていかなければ、これからの高賃金化の時代においては社内で大きな問題を何度も引き起こす可能性があります。
中途で優秀な社員を採用する大事なツールこそが成長シートです。この成長シートのつくり方はグループコンサルティング成長塾で学ぶことができます。成長塾を受講することで、自社の成長シートとして完成しているかどうかのコンサルティングを受けることができます。成長シートをつくりたい方は成長塾にお申込みください。
※「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
2025-06-25 [記事URL]
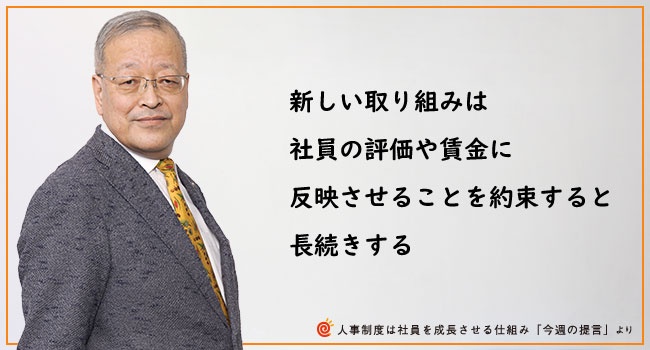
経営者と話をしていると、同じような嘆きの声を多く聞きます。それは「社内で何か新しいことをやっても長く続かない」という嘆きです。そしてその続かない原因は「社員」にあると捉えている場合が多いと感じています。
しかし、これは社員の問題ではなく会社の仕組みに問題があると考えてもらわなければなりません。なぜ新しいことに取り組むのか、会社がその目的を社員に説明していないから続かないのです。
基本的に、新しいことに取り組む目的は何かの成果をより上げるためです。そうした取り組みは、往々にして経営者や幹部が社外のセミナーや研修に参加した後に始めることが多いでしょう。このことに社員は既に気づいているため、誰かがセミナーや研修に行くことを知った瞬間に「また何か始めるつもりだろう」と陰で話しているかもしれません。
会社からすれば、社員の成果を上げるために新しいことに取り組もうとしていますが、この目的を社員に説明していません。この取り組みによって具体的にどのような成果が上がるのかを説明しなければ、社員が積極的に新しいことに取り組むことはないのです。
また、このとき上がる成果については「売上高」や「粗利益」のような大項目ではなく、できる限り細かく分解した項目で説明してください。
例えば「売上高」は「客数×客単価」に分解できます。もし、その新しいことに取り組んで「客単価」は増えても、悪天候など別の原因で「客数」が減少すれば、結果として「売上高」は増えません。新しい取り組みの成果を「売上高」で判断すると、失敗になってしまいます。この繰り返しでは「やっても結果が出ない」と、やがて社員は新しいことに取り組む意欲を失っていくでしょう。
これから取り組むことは「客数」を増やすことなのか、「客単価」を増やすことなのか、新しい取り組みによって上がる成果の種類を分解し、具体的に説明しなければなりません。
また、新しい取り組みによって高い成果を上げた社員がいたとしても、そのことを社員にフィードバックすることを怠っています。新しい取り組みで高い成果を上げることは評価の対象であり、昇給・賞与にも反映されると社員に明示することが必要です。
社員の立場で考えれば、新しい取り組みが評価の対象になっているかどうかはとても重要なことです。そしてそれによって評価が高まり、昇給・賞与に反映されることが明確になっていれば、途中で止めることはありません。
もっとも、どの企業にも「組織原則2:6:2」があるため、新しい取り組みによって成果を上げている社員が、必ず上位に2割存在しています。そこで、この高い成果を上げている社員は新しい取り組みによって高い成果が出たという情報を全社員に共有するのです。
まだまだ成果の上がっていない真ん中の6割と下の2割の社員は、その情報を得ることで成果を上げるイメージを持つことができ、新たな取り組みを続けるようになるでしょう。
組織の中で新しいことに取り組むことは、当然今以上に高い成果を上げるためであり重要なことです。しかし、こうしたことを前もって説明していなかったために途中でうやむやになり、新しい取り組みが止まってしまっていたのです。これを繰り返すことは、組織にとって大きなダメージになります。
そして、新しい取り組みを始めたときの「成果が出なかったから止める」という判断や「成果が上がったので全社で継続して取り組み、もっと大きな成果につなげる」といった判断は会社がしなければなりません。
そこで、新しいことを始めた段階で「継続する」のか「止める」のかを判断する基準を設けることが必要です。成果が上がらない取り組みをいつまでも続けることはできません。経営者はこの判断基準を持ったうえで、社員に新しい取り組みをさせてください。
今後も大きく変化する時代に向け、ますます会社全体で新しいことに取り組む必要性が出てきます。そのためにも、新しい取り組みを評価や昇給・賞与を決める仕組みにきちんと反映させ、前もって社員に説明することを怠ってはいけません。
今までとは全く違う新しい取り組みに挑戦しなければ、組織の存続に大きな影響を与えることを経営者・経営幹部は肝に銘じて取り組まなければならないでしょう。
成長制度で構築する仕組み「成長シート」があれば、こうした新しい取り組みをきちんと評価し、賃金にまで反映させることが可能です。成長制度をまだ導入されていない方は成長塾にお越しください。
※「成長制度」「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
2025-06-18 [記事URL]
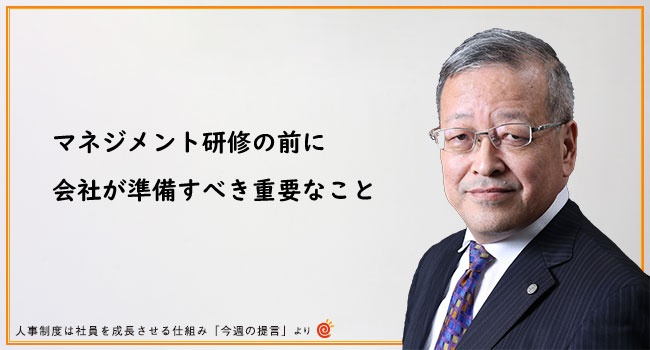
社員が増えて経営者1人で組織運営ができなくなれば、当然社員の成長を促す「マネジメント業務」を担当する上司が必要になります。
しかし、今の上司のマネジメント力に満足している経営者はほとんどいないでしょう。経営者は、上司にはしっかり部下を成長させてほしいという願いを込め、管理者研修やマネジメント研修に参加させているかもしれません。
しかし、こうした研修に参加させる前に会社として明確にしておかなければならないことがあります。それは「部下の成長のゴール」と「ゴールまでのプロセス」です。
通常、社員の成長のゴールは成果の大きさで示すことが多いでしょう。しかし、上司が指導しなければならないのは成果を上げるための過程、つまりプロセスの部分です。このプロセスを指導しない限り、部下の成果は上がりません。
成果を上げるためには、どのようなプロセスが必要になるのかを可視化している会社はほとんどないため、上司はそれぞれ自分の経験に基づいてバラバラの内容で部下を指導しようとします。
その結果、上司によって部下を指導する内容が全く異なるようになります。このままでは、部署間で異動するたびに部下は指導される内容が変わってしまい、異動を機に社員が辞めてしまう可能性があります。上司の指導内容の違いで、退職する社員がいることを知っている会社は少ないでしょう。
そこで、上司には「部下の成長のゴール」と「ゴールまでのプロセス」を示して、そのプロセスを指導するよう、会社全体で統一しなければなりません。
これは、上司を管理職研修に参加させる前にやらなければならないことです。部下が成果を上げるためには何をさせればいいのか、そのためにはどのような知識が必要なのか、どのような考え方で仕事をさせなければならないのか、上司間で指導内容を統一させる必要があります。
これが決まって初めて全上司が部下の成長のゴールを共有化したことになり、そして全上司がそのゴールに向かって部下のプロセスを同じように指導することになります。
また、指導内容を統一した後も、それぞれの上司の部下指導が有効かどうかを確認することが必要です。成長制度で構築する「成長シート」では、部下の成長度合いを「部下の伸びた成長点数」という定量的な結果で見ることができます。この仕組みがない限り、上司に部下指導の力がついているかどうかを確認することはできません。
これからの時代は部下を指導する力が上司に求められます。そのためにも、成長のゴールと指導すべき内容を明らかにしなければなりません。その全てを明らかにし、部下の成長度合いも確認できる仕組み、「成長シート」を作成したい方はグループコンサルティング成長塾にお越しください。
※「成長制度」「成長シート」「部下の伸びた成長点数」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
2025-06-11 [記事URL]
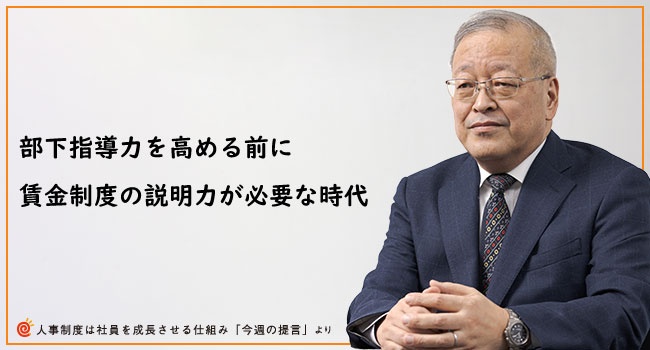
経営者は知らない、最近の現場でよく起きていることがあります。それは社員が上司に対して「賃金」に関する質問をしていることです。
ほとんどの場合、上司は賃金について明確な回答をすることはできません。大体が「社長に直接聞いてください」となるでしょう。
このとき質問した部下は「上司も賃金について分からない」という事実を初めて知るのです。これは相当ショックでしょう。この会社で成長していくことでどれほど賃金が増えるのか、自分の上司も分からない状態で仕事をしているのですから、不安に思わない部下はいないでしょう。このままでは、社員としてこの会社で成長することにますます不安を持つようになります。
口に出すか出さないかの違いはあるものの、全ての社員は賃金に関心があります。こうした賃金に関する質問に、会社の全ての上司が答えられるようになることで、社員は大きな安心感を得ることができるでしょう。
例えば、成長点数(評価点数)が30点の社員が、上司に対して「私が10点成長して40点になったら、昇給・賞与はどう変わりますか?」と質問してきたとします。
この質問に上司が「あなたが10点成長して40点になれば総合評価はCになり、昇給は○○円増え、賞与は○○円増える可能性があります」と明確に答えられたらどうでしょうか?
また、続けて「ただし、あなたの成長点数だけで昇給・賞与が決まるわけではありません。大事なことは会社の経営目標が実現できるかどうかです。つまり、会社の業績によって昇給・賞与の金額は変わります。ですから、ここに集っている社員全員が一緒に成長し、会社の業績を良くすることで全員の昇給・賞与が増えていきます。一緒に頑張りましょう!」と伝えることで、社員は安心してこの会社で成長しようとするでしょう。
どれほど優れたマネジメントスキルを持っていたとしても、この説明ができなければ部下は指導を受け入れることはありません。この会社で成長することでどのように評価され、昇給・賞与にどのように反映されるのか分からないままでは、上司の指導を受ける気にはならないでしょう。これは、社員の本音です。
もし、上司の部下指導力を高めるのであれば、上司が部下に対して賃金について明確に説明できる仕組みをつくることが必要です。それが実現できるのが成長制度です。
今の「社員の賃金を上げなければならない時代」においては、昇給・賞与を支給するために必要な原資を生み出せるほど業績を向上できるかどうかに会社の存続がかかっています。そのためにも、社員には成長と上司による指導が会社の業績につながり、結果として自分の賃金が増えることを明示しなければなりません。
上司のマネジメント力を発揮させるためにも、成長制度が必要な時代になりました。 成長制度をつくりたい方はグループコンサルティング「成長塾」にお越しください。
※「成長制度」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
2025-06-04 [記事URL]
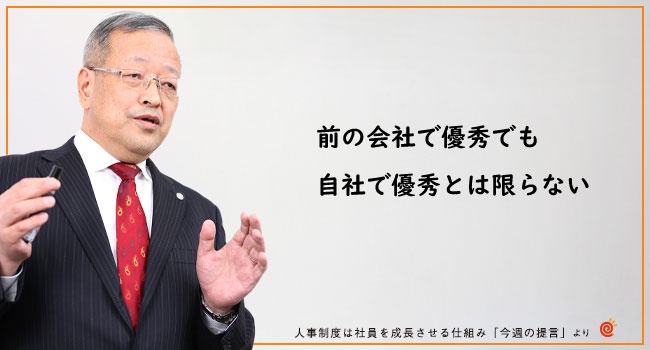
日本における中途採用のテーマは「優秀な社員を獲得すること」です。優秀な社員を採用するために高い賃金を準備している企業も多いでしょう。
ところが、中途採用した社員で「前の会社では優秀だった」という評判とは裏腹に、いざ採用してみると思っていたほど活躍しないケースがあります。なかには採用当初の期待を相当下回る場合もありますが、多くの企業ではその原因が分かっていません。それは大切なことを理解していないからです。
成果の種類が分かりやすい営業職を例に説明すると、営業社員に求められている成果は「売上高」や「新規開拓件数」などでしょう。しかし、この期待されている成果の種類は同じでも、会社によってやっている業務は全く違います。
「新規開拓件数」を増やすために、A社では「電話でのアプローチ」を行っているが、B社では「既存顧客に紹介依頼」を行っているなど、業種と職種が同じであっても会社によって成果を上げるための業務の内容は全く異なるのです。
ENTOENTOの人事制度(成長制度)では、社員に求める成果を「期待成果」として、その成果を上げるために行っている業務を「重要業務」として1枚の評価シート、「成長シート」としてまとめます。
これまで1400社以上の成長シートの作成に携わって約50年が経ちますが、業種と職種が同じでも成長シートの内容が全て同じだったことは一度もありません。期待成果が同じだったとしても、1社1社その成果を上げるためにやっている重要業務は全く異なります。
このように、中途採用した社員にとって「前の会社で成果を上げるための業務」と「転職先で成果を上げるための業務」は全く違う可能性があるのです。
前の会社の成果を上げるやり方のままでは、当然その成果は落ちることになります。前の会社で優秀だと評価されていた社員を採用したとしても、自社では全く成果が出せない理由はここにあるのです。
最悪の場合、前の会社でやっていた業務を一度全て忘れてもらったうえで、自社のやり方を一から学んでもらうことになります。
新入社員であれば一から教えていくことになりますので抵抗されることはありません。中途社員の場合は前の会社では優秀だと評価されていたがゆえに、今までやっていたことを全て消し去って一から新しく学ぶことは、大いなる抵抗感を招きます。
これらを踏まえて、中途で採用することの難しさを感じていることでしょう。しかし、中途でも「自社において優秀な社員」を採用することができる方法があります。それは、中途採用の面接時点で自社の「成長シート」に記載されている業務ができるかどうか判断することです。
「成果が高い」だけで判断してしまえば、中途採用した社員が「この会社で成果を上げる業務はこれまでとは違う可能性がある」ことを全く理解していないまま採用することになります。
今後、中途採用するときには必ず自社で成果を上げるための業務ができるかどうかを確認したうえで採用することが必要でしょう。場合によっては、その業務を一から学んでもらうこともあると説明しなければなりません。
優秀であれば自社の重要業務もすぐできるようになるでしょうが、それまでの期間中はあまり成果が上がらない可能性もあるということを説明したうえで採用しなければなりません。
自社の成長シートをつくっておかなければ、中途採用した際に問題が発生する恐れがあります。特に、成果が高いからといって高い賃金を約束してしまうと、社内全体に影響を及ぼすほど大きな問題を引き起こします。
中途採用で失敗しないための成長シートをつくるためにも、グループコンサルティング「成長塾」にご参加ください。
※「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
2025-05-28 [記事URL]
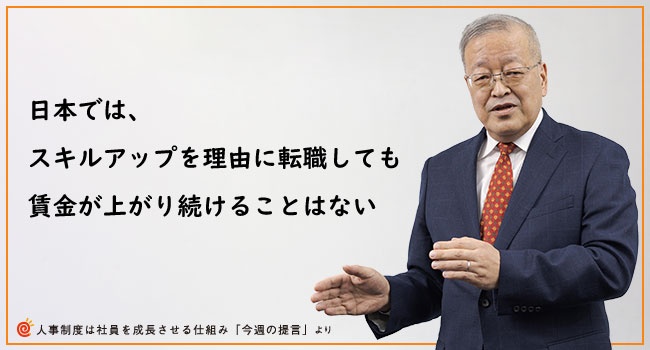
転職を考えている社員が確認している情報の一つは「転職後の賃金」です。現在より賃金が上がる会社を探しています。
「賃金が上がるから転職する」
これは普通の判断であることは間違いないでしょう。
しかし、日本では転職後も継続して賃金が上がることは約束されていません。日本には欧米のような「産業別組合」がなく、各業界における賃金相場が存在していないからです。つまり、スキルアップによる賃金の上昇が約束されていません。
異業種への転職は賃金が上がらないのは当然だと思えますが、同業種への転職でも相場がないために賃金が上がる保証はないのです。このことを経営者は説明していません。
また、転職時の賃金が今よりも高いとしても、その賃金がその後も増える保証はありません。これは採用する会社側の視点で考えれば分かることです。
例えば、中途社員を採用する際、経営者は「同業界の経験者であれば高い賃金で採用したい」と思うでしょう。しかし、日本では先述した「産業別組合」がないために、同業種であっても会社によって「優秀な社員像(評価すること)」が全く異なります。
その結果、経験豊富だと思って採用したら自社のやり方とは全く違い、新卒同様に一から仕事を教えなければならないケースが起こり得るのです。採用した社員によっては前勤務先でのやり方をそのまま続けてもらっては困るため、一度そのやり方を全て捨てさせなければならず、新卒を採用した方がまだ良かったという事例がたくさんあります。
こうした中途社員の賃金は結局払いすぎているとなり、大きな問題になっています。
このことを知らずに、賃金の高さだけで転職する社員が非常に多くなっています。転職によって賃金は上がることはないと教育することが、これからの経営においてとても大事な社員教育の一つとなるでしょう。
そもそも、会社が高い賃金を提示するのは即戦力募集という意味合いがとても強いからです。入社当初は高い賃金であったとしても、その後も継続して賃金が上がるかどうかを説明できる会社はほとんど存在しないのです。
改めて、自社の社員には「日本では転職によって賃金は増えることはない」としっかり説明しなければなりません。そのためには「成長制度」の「成長シート」がお役に立ちます。
成長シートには「優秀な社員像」が記載されています。どのようことを会社が評価し、どのようなことをすることで成果が上がるのか、同業種であっても内容は会社ごとに全く異なります。もし、転職先に成長シートがあったとしても内容が全く異なるため、同じように評価して賃金を決めることはできないと社員に説明することが必要でしょう。
この会社には「この会社独自の成長シート」があり、3階層のステップを踏んで成長することで賃金が増えていくと明確に説明できる制度が「成長制度」です。そのためにもこの「成長制度」の導入は重要と言わざるを得なくなりました。
「成長制度」の導入をお考えの方はぜひグループコンサルティング「成長塾」にお越しください。お申し込みは簡単です。
※「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
2025-05-21 [記事URL]
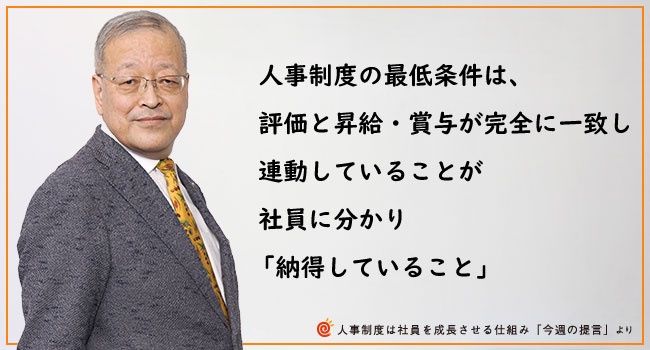
人事制度は一般的に、評価を決めて昇給・賞与を決めるための制度です。ところが、この評価と昇給・賞与が一致している人事制度はほとんどありません。意外に思われる経営者は多いでしょう。そのため、社員は「成長した」と会社から評価されたとしても、それによって昇給や賞与がどれぐらい増えるのか、まったく分からないのです。「まったく」です。
昇給・賞与に関心がない社員はいないでしょう。なかには、上司に対して「どうしたら昇給・賞与が増えますか?」と聞いてくる部下もいるかもしれません。しかし、上司に質問しても答えを得られることはまずないでしょう。それは、上司自身も評価と昇給・賞与がどのように決まっているのか、まったく分からないからです。
質問した部下は、上司でさえ分かっていないことに気づくことになります。部下にとっては驚きでしょう。実は、これが人事制度に対する不平不満の温床となっているのです。
社員は「早い」「遅い」の違いがあったとしても確実に成長しています。その社員の成長に伴って、経営者は昇給・賞与を増やしていることは間違いないでしょう。しかし、このことが仕組みになっていないために、社員は評価と昇給・賞与の関係を理解することができていません。
つまり、社員は「この会社で何年働いても自分の賃金がどうなるか分からない」状況で仕事をしているのです。相当不安でしょう。
今までのように、企業によって賃金がそれほど大きく変わらなかった時代であれば、それでも問題はなかったかもしれません。ですが、今は多くの企業、特に大手企業が初任給と中途採用の賃金を上げて採用活動を行っています。こうしたニュースは多くの中小企業の社員の耳にも届いていることでしょう。
賃金が高いことは、社員にとっては願ってもないことです。しかし、多くの場合は欠員補充の募集だから採用時の賃金が高いわけであって、評価の結果として賃金が高いわけではありません。
日本では、欧米のように産業別に賃金相場が決まっていません。そのため、欧米のように転職する度に賃金が上がることはほとんどないのです。
ですから、転職したことで賃金が上がったとしても、それはそのときに限ったことであり、そのまま賃金を維持するには相応の厳しい条件がつく可能性は否めません。残念ながら、日本では転職によって賃金を上げていくことは現実的ではないのです。
その教育を、経営者は在職社員に対してしなければなりません。このことを教育するためにも、自社の評価と賃金が一致している仕組みをつくったうえで社員に説明しなければならないのです。
ENTOENTOの成長制度では「成長シート」の評価(成長点数)で昇給・賞与を決定します。成長シートで社員を評価し、その結果である成長点数によって昇給・賞与がいくらになるのかが全て仕組みになっています。仕組み上で評価と賃金が完全に連動させることができるのです。
この説明ができることで、今いる社員を定着させるだけでなく、採用活動でも活用することができます。ますます厳しくなっていく採用環境においても、社員が採用できるようになっていくのです。
特に「当社では、社員が成長して会社の業績が向上することで賃金がどのように増えるか」を示した「モデル賃金」を用いて明確に説明できることが、採用において有利となる仕組みといえるでしょう。特に、中小企業には有利な仕組みです。
賃金を上げることはとても重要です。しかし、こうした評価と昇給・賞与が完全に連動していることが明確に分かる仕組みづくりがそれ以上に重要であると早く気づいてください。
この仕組みをつくるのは簡単です。グループコンサルティング「成長塾」にお越しください。
お申し込みは簡単です。
※「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
2025-05-14 [記事URL]

全ての会社にあるものは「組織原則2:6:2」です。高い成果を上げている社員が2割、まあまあの成果を上げている社員が6割、これから成果を上げる社員が2割います。これは全ての会社に共通する相対評価です。そのため、10年前も今も、そして10年後にも存在する組織原則になります。この組織原則は企業規模に関係なく、全ての会社に存在しているものです。
しかし一方では、全ての会社に存在しながらほとんど活用されていないものがあります。それが、高い成果を上げている社員のやっていること(業務)です。
「この会社で高い成果を上げている社員が何をして成果を上げているのか?」
これほど重要なことを、可視化も共有化もしていないのが現状です。
一般的に、会社の業績を上げようとするときは「今、当社でやっていない新しいことに取り組まなければ、今まで以上の業績にはならない」と考えるでしょう。しかし、それは当然先ほどの組織原則2:6:2における上位2割の優秀な社員でもやっていないことに取り組むことになります。
そのため、実際に社外で学んだ新しい取り組みを始めたとしても、成果が上がるかどうかは「やってみなければわからない」というリスクを持っています。
もともと私たちは、今まで慣れ親しんだことを継続しようと考えるため、新しいことに取り組むのには若干の抵抗があるでしょう。さらに、その抵抗感を持っているのが現在成果を上げている上位2割の社員だとすると、組織全体への浸透や実行には相当の年月が必要になります。さまざまな新しい取り組みが頓挫する理由の一つは、ここに原因があるといって間違いありません。
ところが、会社全体の業績を上げる方法として「上位2割の業務内容を可視化し共有化する」ことであれば、2つのメリットがあります。
1つは、自社内の社員が教えられるようになることです。
成果を上げている社員は「自分が何をして成果を上げているか」が分からないまま高い成果を上げています。概ね日本では、この社員は優秀だと評価されて中堅階層にステップアップすることになります。
しかし、中堅階層にステップアップしても成果を上げられた理由を正確に把握していないため、上手に部下を指導することができません。一般階層の時点で「成果を上げるためにやっていること」がはっきり分かれば、自分がこれまでやってきたことを説明するだけで部下が成長させる有効な部下指導となり、やがて成果を上げさせることができるのです。
もう1つは、社内の社員がやっている成果を上げる業務に対して、社員の誰もが「自分にもできる」と考えるようになることです。
何事も、新しいことに取り組む際には前段階で「できるかどうか」を考えます。これまで誰もやったことのないことであれば「自分にはできない」と思ってしまうでしょう。しかし、すでに自社の社員がやって成果を上げているのであれば「自分にもできないことはない、きっとできる」と判断するでしょう。
全ての社員がこの高い成果を上げている社員の業務を真似る、そしてときには優秀な社員から教えてもらうことで、やがて全社員が実行できるようになるのです。これは成果を上げるのにあまり時間は必要ありません。
この2つのメリットを理解していただければ、すぐにでも成果の上がっている社員の業務を可視化して共有化しようと考えるでしょう。そのためのツールが「成長シート」です。
成長シートは今いる優秀な社員をモデルに作成します。優秀な社員を可視化することで「何をしていたのか」「そのためにどのような知識技術が必要だったのか」「どのような考え方で仕事することが必要なのか」といった成果を上げるために必要なことが分かります。
モデルとなった優秀な社員を成長シートで評価すると、80点以上になります。全ての社員が80点以上を目指して成長シートに書かれたことを実行するようになるのです。社員はこれまで以上に意欲的に成長することになるでしょう。それは、全ての社員が成長したいと考えている証です。
これから10年以上業績を上げ続けることができる成長シートの作成はグループコンサルティング「成長塾」で学ぶことができます。 今すぐ業績を向上させて賃上げ率5%を実現したい方は、ぜひこのグループコンサルティング「成長塾」にお越しください。賃上げ率5%以上の中小企業が続出しています。お申し込みは簡単です。
※「成長シート」はENTOENTOの登録商標です。
●コラムの更新をお知らせします!
コラムはいかがでしたか? 下記よりメールアドレスをご登録いただくと、更新時にご案内をお届けします(解除は随時可能です)。ぜひ、ご登録ください。
株式会社ENTOENTO
〒196-0003
東京都昭島市松原町
1-18-11
ダイヤヒルズ2F
TEL:042-542-3631
FAX:042-542-3632