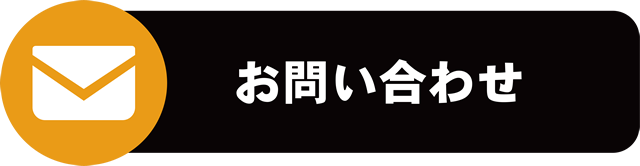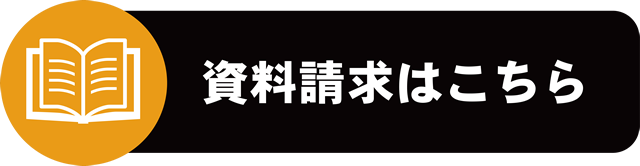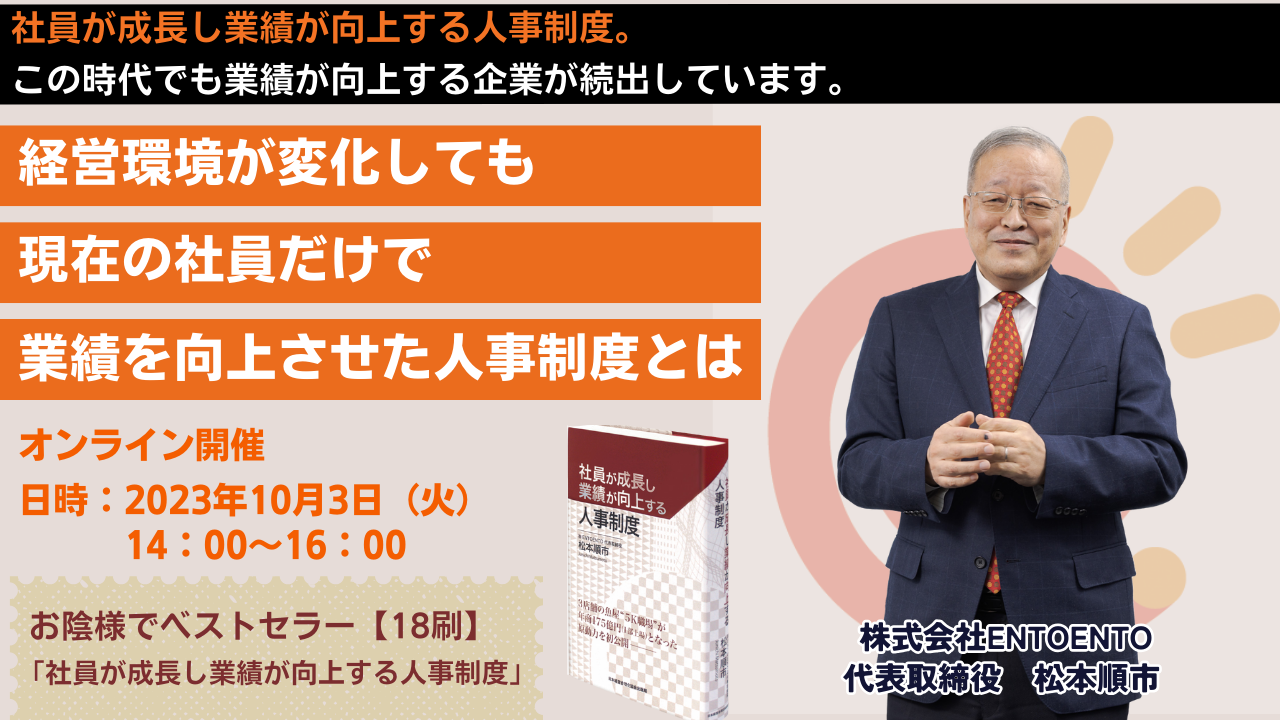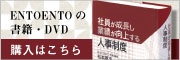第176話 飛躍的に生産性が向上できる会社の特徴
2023-09-26
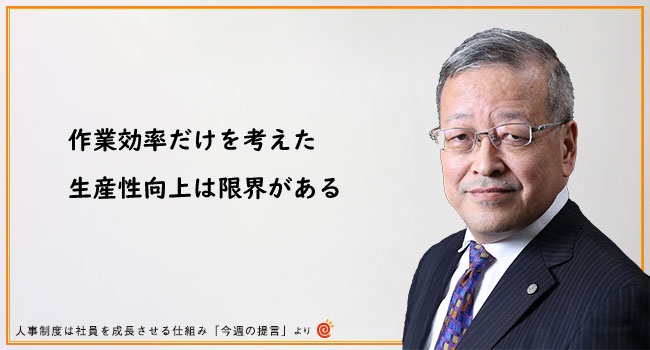
生産性を上げるために、作業効率だけを求めていても限界があります。
1時間当たりの労働生産性は、粗利益÷労働時間で計算することができます。生産性を上げようと考える多くの人は、この計算式の「労働時間」を短くすることを考えます。
仕組みをつくることでこの労働時間を短くすることは可能です。極端なことをいえば、仕組みによって今やっている仕事をやらなくても成果を上げられるようになる可能性はありますが、ただし、今やっている仕事を全てなくすことは現実的に考えて無理でしょう。
しかし、新商品を今まで以上の高付加価値で販売することは可能です。つまり、生産性向上は労働時間を短くする以上に、高付加価値な商品・サービスを開発することに取り組むことなのです。
新しい商品や新しいサービスを開発するとなると、とても難しく、専門的な知識がなければできないというイメージがあるでしょう。しかし今いる顧客のニーズを分析し、それに応えられる商品・サービスを新たに開発すればいいだけの話です。
その顧客ニーズはどこにあるかというと、現場で働いている社員とお客様の間に発生しています。お客様と会話をしていると「○○が欲しい」「□□で困っている」等々、お客様の困っていることやニーズを直接聞けることがあります。
優秀な社員はその声を拾ってニーズに応えられる新商品・サービスを提供する努力をするでしょう。さらに優秀な社員は、実際の要望だけでなく顧客自身も気が付いていない「潜在ニーズ」を発見しています。これにより顧客満足度がとても高く、他社には真似できないような新商品・サービスを提供しているのです。
つまり、生産性を高めるために大切なことは、お客様も気が付いていない潜在ニーズをとらえ、それに対応できる商品・サービスを提供することです。
このこと自体は高付加価値の新商品・サービスを提供できることにつながるため、時間の短縮を考える以上に大きな生産性向上になります。独自的なものであれば、値引き交渉はされません。
一般階層の社員は自分で仕事をして顧客に喜んでもらう、プレーヤーの階層です。しっかりと顧客のニーズを捉え、それに対応することがこの会社の使命であると学べる階層といえるでしょう。
このように成長することで、会社の20年後30年後の事業展開を、既に一般階層の現場で培ってきていることになるでしょう。
この顧客のニーズは日々変化していきます。その変化を把握できるのも、顧客と直接やりとりをする一般階層の社員でしょう。この変化するニーズに対応している社員は「環境適応社員」と呼べます。
今は「マネジメント」という言葉で上司が部下を指導して成果を上げていることばかり強調されています。これでは上司が過去のニーズを基に部下指導をするため、部下は上司以上に成果を上げることはできないでしょう。
上司は現場の部下が把握した顧客ニーズを早期に収集し、新商品・サービスの検討をすることが求められます。
生産性を上げるための対策は立てていますか?
※ 成長塾についてはこちら ※ 資料請求はこちら ※ 松本順市の書籍はこちら