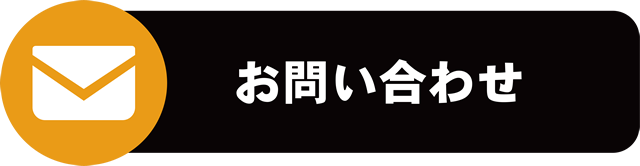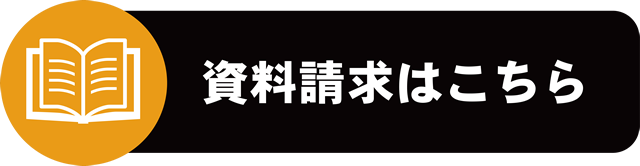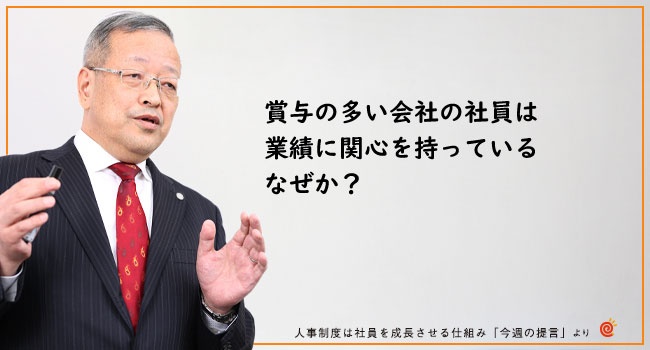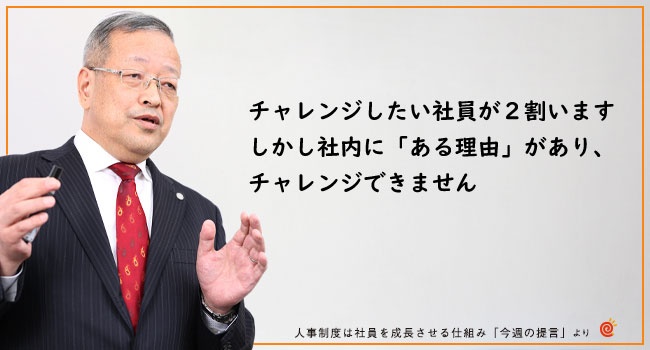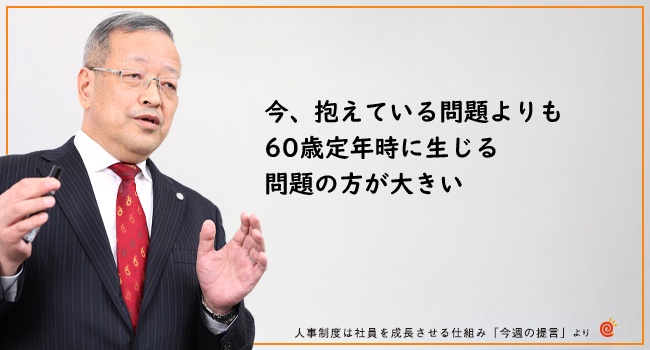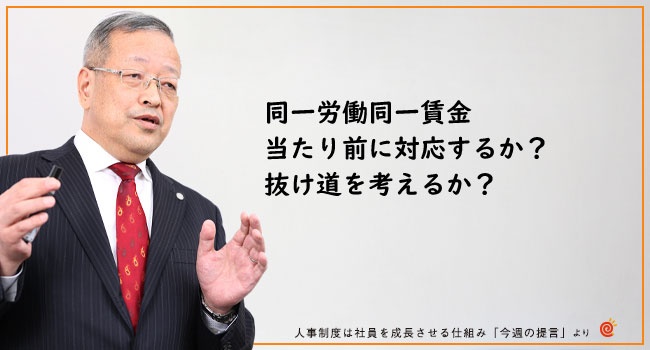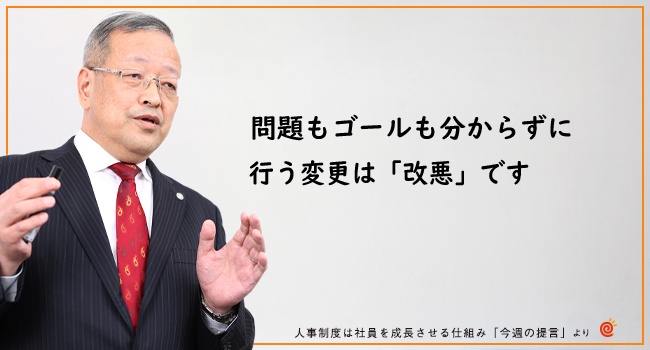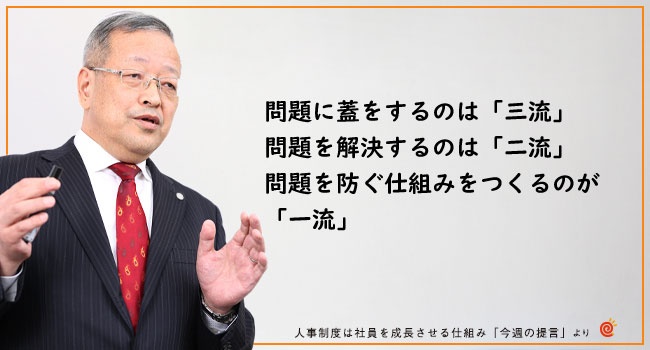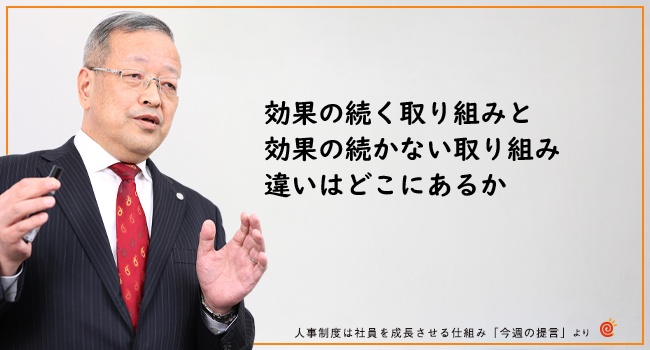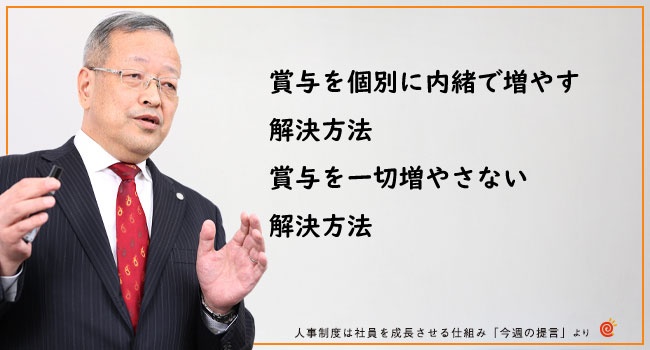第39話 嫌な人事の問題を2度と発生させない方法とは
2020-10-20 [記事URL]
「最近、社員から不平不満の声が出るようになり、頭が痛いです。この不満を上手になくす方法はないでしょうか?」
この質問は、社員数が増えてきた会社の経営者から投げかけられます。だんだん社員が増えてくると、社長と社員のコミュニケーションの時間が減り、社長の想いが伝わらなくなっていくからです。そのため、コミュニケーション不足から誤解やすれ違いが生じ、不平不満が発生しやすくなるのです。
この不平不満を「有難い情報だ」と思えるかどうかで会社の未来が大きく変わってきます。
人事上の問題は通常「臭い物に蓋をする」と言われるくらい、見ないふりをしてしまうものです。また、蓋をしたいと思うくらい、経営者にとって頭が痛いことでもあります。対応したとしても社員を説得しておしまい、というパターンも多いでしょう。
そのため、同じ問題が繰り返し起きることになります。人のことで悩む経営者にあることを尋ねるとそれがわかります。
「これまでどのような人事上の問題が起きましたか?」
この質問に、すぐに的確に答えられる経営者は意外と多くありません。だいたい社員を説得したら、その問題をすぐに忘れてしまっているからです。だから、また同じ問題が発生するのです。もっとも、嫌な問題はすぐ忘れたいと思う心境も十分に理解できます。
社員からの不平不満は、実はお客様からのクレームと全く同じです。期待をしているからこそ、お客様はクレームを言ってきます。もう二度と付き合う気がなければ、クレームを言ってくることはないのです。会社に期待することを辞めた社員は、黙って去っていきます。または、当たり障りのない理由を言って辞めていきます。
「クレームはダイヤモンドの原石」
と言われるように、お客様からのクレームにはしっかり対応することを重要視しているでしょう。そして同じクレームが発生しないように仕組みを考えているでしょう。では、社員からの不平不満も同じように、一つひとつ解決しながら仕組みづくりをしているでしょうか。
たとえば、社員が定着しないという問題はどの会社にとっても大きな問題でしょう。新卒社員は入社して3年以内に30%辞めるといわれていますが、この問題を解決することができる会社はどれくらいあるでしょうか。
新卒社員がが辞めてしまう理由は、会社によって様々かもしれません。しかしどのような理由があったとしても、解決策を知る方法は1つです。
それは新卒社員が我が社で何を問題と思っているかを聞くことです。たったそれだけです。
何が問題なのかがわかれば対処できます。そして対処方法がわかったら、その都度対処するだけで終わるのではなく、問題自体が起きない仕組みをつくるのです。
たとえば、新卒社員が「将来が不安です」と言ったとします。恐らく経営者は将来が不安ではないことを一生懸命説明することになるでしょう。そして説明を受けた新卒が「よく分かりました」と言って次の日から元気よく仕事をするようになったら安堵するでしょう。それはかまいません。ただし、安堵しっぱなしは危険です。
実際にクレームを伝える人は不満を感じた人のうちたった4%で、残りの96%はサイレントクレーマーだと言われています。つまり、1人でも先ほどの不安を抱えている社員がいるのであれば、他に24人も同じ不安を持っていると考えなければならないのです。
ですから最低限、経営者が新卒社員に話したことを、社内に共有する必要があるでしょう。
たとえば、「我が社には一般職層、中堅職層、管理職層があり、この成長階層を成長していくことになります。あなたは自分の好きなプレーヤーの仕事がしたくて入社したかもしれない。けれど順調に成長していけば10年後くらいに優秀な社員として中堅職層にステップアップすることになり、またさらに10年後くらいに管理職層にステップアップすることになります。20年を過ぎた頃には、私と一緒になってこの会社を通じて世の中に大きな貢献をしていく、そのように働く内容が変わっていくことになります」と話したとします。
それを同じように社内に手紙やミーティングなどで共有しなければならないのです。
そしてさらに私が行っていただきたいと考えているのが、次の仕組みです。先ほどのように話したとすれば、
「我が社には一般職層、中堅職層、管理職層がある」⇒3階層の成長シートをつくる
「一般職層、中堅職層、管理職層があり、この成長階層を成長していくことになる」⇒ステップアップ基準をつくる
と、問題解決の仕組みをつくってほしいのです。
問題が解決したと言えるのは、社員が納得して社長室を去ったときではありません。仕組みをつくり、同じような不平不満を持つ社員が1人もいなくなったときです。
悲しいことですが、社員は経営者の言ったことを本当は信じていません。口ではどんないいことでも言えることをわかっているからです。しかし、仕組みは違います。仕組みは経営者と社員との約束です。仕組みとして示され、その通りに実行されたとき、初めて社員は「社長が話していたことは本当だったのだ」と安心します。
問題があったら、すぐにそれを仕組みにできるかどうか。これが重要なポイントです。
私は前勤務先で人を定着させる仕組みをつくりました。それによって70%だった定着率を95%まで高めることができました。上司の指導力が高まったことも、給料が上がったことも関係ないとは言いません。しかし定着率95%は、定着率を高めるための仕組みをつくったからなのです。
さあ、では、定着率を高める仕組みをどれくらいお持ちでしょうか? ぜひ今日考えてください。